問いは未来を創るのか?
―〜未知を照らす「創造の触媒」としての問い〜―
京都産業大学生命科学部 産業生命科学科教授
NPO法人ハテナソン共創ラボ代表理事 佐藤 賢一(さとう けんいち)

人工知能(AI)の活用が広がり、人間が頭脳を使わなくてもさまざまな「答え」が無限に生み出せる時代になりつつある。
翻って、答えに先立つ「問い」はどうだろうか?とりわけ、私たち自身が「自分ごととして取り組みたくなる問い」を、AIは作れるのだろうか?そして、不透明な時代に正しい答えを導く「適切な問い」とは何だろうか。
「問い」の可能性について着目し、「問いづくりテクニック」(The Question Formulation Technique=QFT)の手法を啓蒙し、教育・組織変革などの場面で活躍できるファシリテーター人材を育成するNPO法人「ハテナソン共創ラボ」代表理事の佐藤賢一さんに、QFTの価値とそのワークによる行動変容、「未来をつくる問い」などについて話を聞いた。
QFTとの出会いと魅力
QFTについてまず、簡単に教えていただけますか?
佐藤
QFTは、アメリカで開発された問いづくりメソッドの基本プロセスです。開発者は、コミュニティ・オーガナイザー・都市計画家でもあるダン・ロスステインと社会活動家のルース・サンタナの2人です。アメリカの市民運動から誕生したもので、あらゆる人々が民主的な意思決定に参加できる仕組みなのですね。これまでは教師や指導者が生徒や参加者に対して、予め決めた問いを発してきました。生徒や参加者は与えられた問題を解き、「正解」を探します。しかしQFTでは、そのスタイルが逆転します。生徒や参加者が「問いを作る主体」となり、これまでの指導者は、問いをつくるための支援者に回ります。
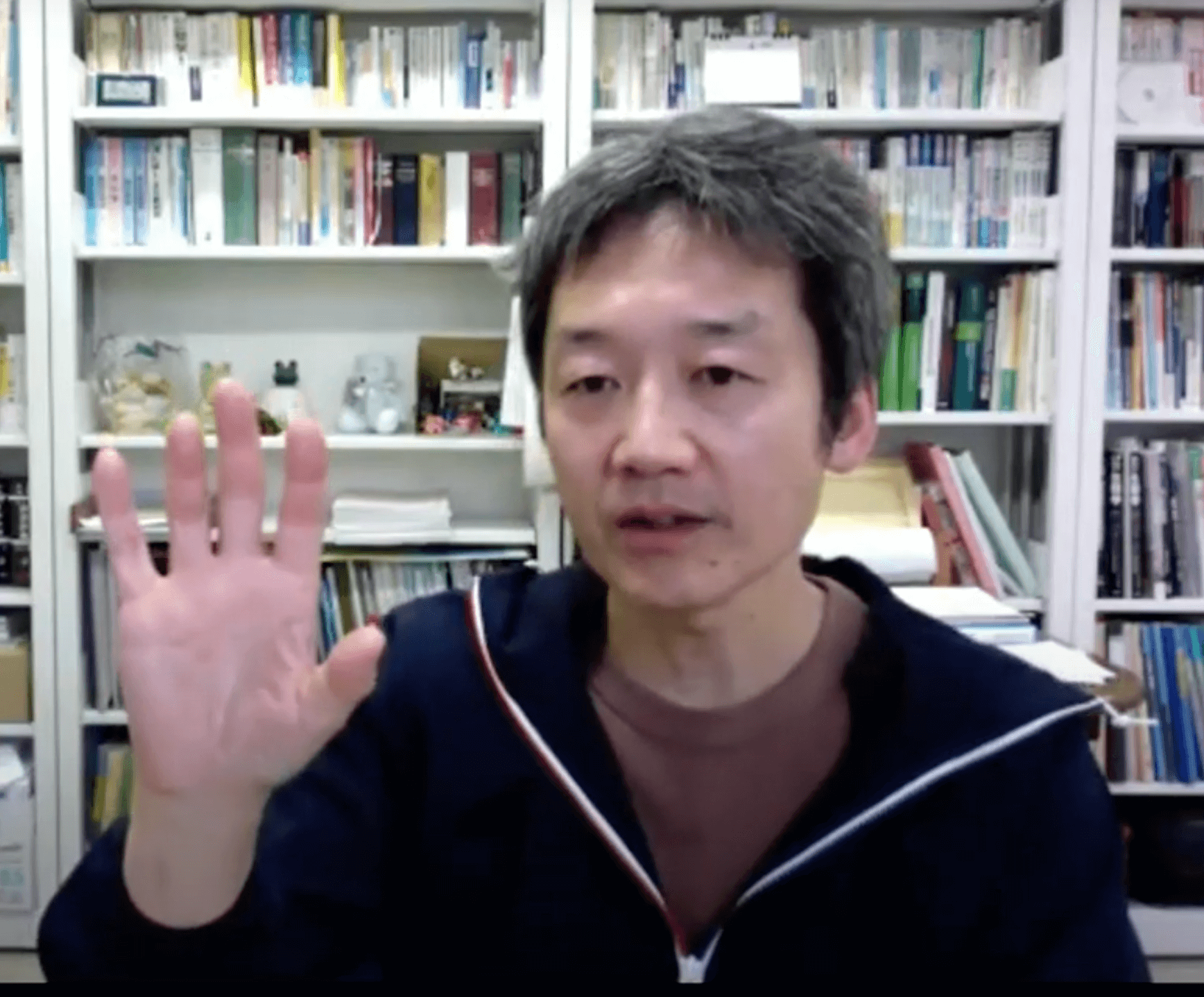
どんなメソッドでしょうか?
佐藤
やり方はとてもシンプルです。小学生でもできるので、学校の授業で活用されています。プロセスは①問いをたくさん出す②問いを「閉じた/開いた」で分類する③問いを変換する④重要な問いを3つ選び、選んだ理由と次のアクションを考える-この4段階です。
佐藤さんとこのメソッドとの出会い、どうしてQFTを伝える活動を始めたのか、きっかけや理由を教えてください。
佐藤 2016年2月、勤務先の大学内書店をぶらついていたら「たった一つを変えるだけ〜クラスも教師も自立する『質問づくり』」(新評論刊)(※1)というダンとルースが書いた本が目に飛び込んできました。それが出会いです。何の予備知識もありませんでした。立ち読みをしてみて「これに違いない」という感覚がありました。学習者が、外から与えられた問いに対して答えるのではなく、学習者自身が問いを立てる。その「学習者中心主義を中核に置く」という考えが徹底していました。まさに「たった1つを変えるだけ」なのですが、その発想の転換にひかれました。学外などでワークを実践してさらに感動が深まり「この方法を広げるのは自分の使命」と思い、NPO法人まで作ってしまいました(笑)。
QFTの「自分ごと化」プロセス
NPO法人「ハテナソン共創ラボ」をつくり、大学に留まらない活動をされています。このQFTについて学び、体験した参加者の変容をはじめ、気づいた点があれば教えてください。
佐藤 QFTはとてもシンプルなメソッドで「問いをたくさん出す」という行為は誰にでもできるので、とてもフレンドリーなワークと言えます。しかし「たくさん作ろう」としても作れなくなる場合にぶつかります。そんな「問いが作れなくなる時」がまずとても大切です。その時「自分はテーマについて何を知っているのか/知らないのか」「問いって何だろう」「自分の立てた問いにはどんな意味があるのだろうか」ということなどに意識が自然と向いてきます。
問うという行為そのものを考えたり、自分がテーマについて適切な問いを立てられるのかどうかについて考えを巡らしたりする時間ですね。
佐藤
そうですね。そうしてテーマと問いに向き合い、考えながら「自分ならでは」の問いをさらにつくっていきます。こうしたプロセスを経て納得のいく問いを立てられた時、参加者は「自分にも(自分が解きたい)問いを立てる・発見することができた」という自己効力感を得ているようです。
その自己効力感は、その後の行動に影響を与えますか?
佐藤
「私はこれが知りたかった」という気づき、「解きたい問いをつくることができた」という自己効力感が、問いを掘り下げたり、答えを探したりする行動を促します。つまり「自分ごと化」するにあたって、QFTはとてもパワフルなツールなのですね。
QFT実践時の重要な要素として「問いの焦点」があります。何について問いを出すかという「問いの焦点」は、参加者で決めることも、組織内の誰かが決めてそれに取り組むこともできます。私たち(BackcastingLab編集部)も、QFTをする際、適切な「問いの焦点」の設定にとても注意を払っています。
佐藤
問いの焦点を決定する際には、ワーク設計者がまさにどれだけバックキャスティングでテーマを捉えているのかが問われます。何のために今回、参加者は問いをつくるのか?参加者はそのテーマについてどれくらい知識があるのか?QFTを実践する際に、ワークの設計者がテーマを掘り下げることが必要です。
設定のポイントは「生み出された問いが活用されるシーン・出口を意識しているか」「問いを引き出す”引き金”となる情報として適切かつ有効か」という点。その際に求められるのは、参加する学習者の立場になってシミュレーションする姿勢です。組織を変える立場・そのための研修を企画する立場・ワークを設計する立場の人は、もともと質問をしたり議論したりすることに慣れているので「問いが出ない」という状態がなかなか理解できません。けれども、ワークに参加する学習者の状況をよく知り、前提知識なども考慮して、学習者の立場で適切な「問いの焦点」を考えることが重要です。自分で問いを立てることと問いづくりの支援をすることは違うのです。
QFTには、問いを「閉じる/開く」で分類するプロセスがありますね。それぞれの問いのタイプにどんな意味があり、なぜこの分類をするのか教えてください。
佐藤
問いを出し切った後に、改めて「(テーマについて)知りたいことを知るために適切な問いになっているか?」というのを見つけるフェーズがこの工程です。何をどのようにたずねれば自分や相手の知りたいことがわかるのか?解決に役立つのか?という視点で問いを吟味します。
「閉じた問い」の典型は、選挙時の出口調査ですね。「どの候補者に入れたのか?・支持政党は?」という質問の答えは1つです。質問者側の知りたい情報が明確です。
対照的に「開いた問い」は、理由や手法・目的をたずねるような内容で、一言では言い表せない多様な答えを導きます。
どちらがいい・悪いではありません。テーマについてなじみがないと開いた問いが多くなり、前提知識が多いと仮説を入れた閉じた問いが多くなる傾向があります。開いた問いには、原点や動機付けを問う内容もあり、閉じた問いはテーマの解像度を上げる要素が含まれるなど、それぞれ相補的です。どちらの問いが多いのかによって、自分やチームの特徴も把握できます。
問い自体を俯瞰して見直し、その上で「問いを変換する」という次のステップに進むのですね。
佐藤
問いの変換は「閉じた質問は開き、開いた質問は閉じる」と説明されていますが、最近は「問い重ね」「クエスチョンマッピング」「問いの曼荼羅」と表現する方が本質的だと感じています。機械的に「Close⇔Open」をすることが目的ではないからです。これまで出された問いと向き合いながらさらに、オリジナルな自分の問いを作ることが目的なのです。「自分が作った問いを他者に見せた時に理解できる問いになっているか?」という観点を持ちつつ、1つの問いの要素を出発点に、さらに新たな問いを重ねていく。この作業を通じて、参加者は「問いが自分のものになる」という体験をしていきます。
未知を照らす創造の触媒
QFTによって問いが「自分ごと化」されたとします。問いを出すだけにとどまらず、未来を変えていくアクションにつなぐプロセスを、佐藤さんはどのように考えていますか。
佐藤
人は自分が作った自分だけの問いに答えたくなります。その先を知るために何をすればいいかを考え始めます。つまり、答えを探すプロセスを思い描き始めます。それはリサーチクエスチョンといえますし、その問いを起点にして仮説をつくり、検証するサイクルをデザインすることが新しい未来をつくる1つのアクションになるのではないでしょうか。そのサイクルを私は「ハテナソン」(問いづくり)、「アイデアソン」(仮説づくり)、「ハッカソン」(プロトタイプづくり)と整理しています。これをぐるぐると回して、知りたい答えに近づいていけたらと考えています。

AIがさまざまな「答え」を幾通りも出してくれる状況が生まれています。そうした時代に、人間が考える問いにはどんな役割・可能性があるでしょうか?
佐藤
AIが今後、さらに進化していくことは間違いありません。けれども私は、人間が「問いを問い続ける」という行為が、人と社会がよりよくなっていく仕掛けであることを信じています。なぜなら「自分自身が学んでいける自分である」という自己効力感や「ほかの人や社会とつながって学びが深まっている」というつながりの意識を深化させる可能性があるからです。
イノベーションや創造における「問いの役割」について、考えを聞かせてください。
佐藤
QFTでは、自分自身の価値観や経験・知識が「問い」の形で見える化されます。「今、何が分からないか」がわかるということでもあります。
また、個人ではなくチームで取り組めば様々な人の視点や経験・知識を問いの形で共有されます。そうやって、さまざまな問いが重なり、リソースが組み合わさり、新たな問いを展開してつくっていくなかで「まだ、だれも問いかけていないこと」という未知の世界があることがわかってきます。
クリエイティブな問いとは、未知の概念や現象を照らす光であり、さまざまな価値観や知識をつなぐ触媒になるような問いだと言えるのではないでしょうか。
最後に、佐藤さんにとって「大事な問い」とはどのような問いでしょうか?
佐藤
「ずっと問い続けられる問い」ですね。いつまでも考え続けたい問いを持っていることで、なぜか安心するのです。
ありがとうございました。

プロフィール
1965年北海道生まれ。神戸大学大学院理学研究科生物学専攻修了。2008年から京都産業大学教授。専門は発生情報学。生物が「どのようにして生まれ、どのように死ぬのか?」というテーマのもと、受精(生物発生の起点となる現象)とがん(細胞レベルの死を克服した存在であり、かつ個体を死に至らしめる存在)の2つの生命現象を研究している。NPO法人ハテナソン共創ラボは、2017年設立時から代表理事を務める。

